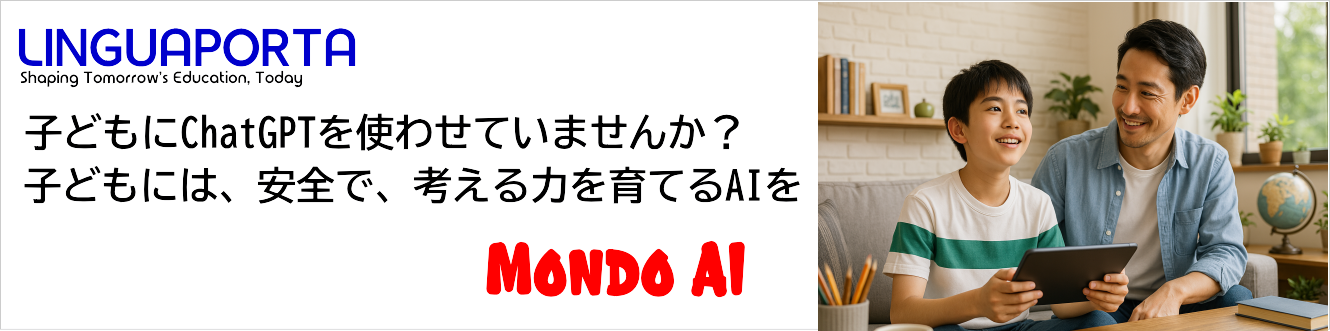はじめに:言語習得理論の転換点
人間がどのようにして言語を身に着けるのかという問いは、言語学、心理学、認知科学における中核的な課題です。従来の理論では、子どもは抽象的な文法規則や語彙カテゴリーを獲得し、それらを基に新しい文を生成すると考えられてきました。しかし、リバプール大学のBen Ambridge教授が2019年に発表した論文”Against stored abstractions: A radical exemplar model of language acquisition”は、この常識に真っ向から挑戦する理論を提示しています。
本論文は、言語習得研究における既存の理論的枠組みを根底から見直すことを求める野心的な試みであり、その主張は言語習得分野に大きな波紋を投げかけています。
研究者の背景と研究の位置づけ
Ben Ambridge教授は、リバプール大学心理科学部に所属し、ESRC言語・コミュニケーション発達国際センター(LuCiD)の中核研究者として活動しています。子どもの言語習得、特に語形変化や構文習得の分野で多数の実証研究を手がけ、国際的に高く評価されている研究者です。
この論文が掲載された『First Language』誌は、言語習得研究における最も権威ある学術誌の一つであり、通常は特定の現象に焦点を当てた実証研究が主流です。しかし、本論文は50ページを超える大部な理論論文として、言語習得研究全体の理論的基盤を問い直すものとして異例の扱いを受けています。
論文の主要な主張:例示記憶理論の提案
Ambridge教授の中心的な主張は、従来の言語習得理論が前提とする抽象的な言語表現の貯蔵という概念を完全に否定し、代わりに「極端な例示記憶理論」を提唱することです。
従来の理論では、例えば英語を学ぶ子どもは「主語-動詞-目的語」という抽象的な構文パターンや「動詞」「名詞」といった語彙カテゴリーを獲得し、これらを組み合わせて新しい文を生成すると考えられてきました。生成文法学派では生得的な文法知識を、用法基盤理論では入力から抽出された抽象的パターンを想定していますが、いずれも何らかの形で抽象化された表現の貯蔵を仮定しています。
これに対し、Ambridge教授は人間の言語知識が具体的な言語使用例(例示記憶)の集積であり、抽象的な規則や表現は一切貯蔵されていないと主張します。新しい文の理解や産出は、記憶された具体例との類推によってその場で行われるというのです。例えば、「She’s dancing」という文を理解したり産出したりする際、話者は「She’s running」「She’s jumping」「He’s dancing」といった記憶された具体例との類推を瞬時に行うとされます。
理論的貢献の評価:統一理論としての野心
本理論の最も重要な貢献は、言語習得の諸現象に対する統一的な説明を提供しようとする点です。従来の研究では、語意習得、語形変化、統語習得、音韻習得などが個別の研究領域として扱われ、それぞれ異なる理論的枠組みで説明されてきました。
Ambridge教授は、語意から音韻に至るまでのすべての言語現象を、同一の認知メカニズム(例示記憶と類推)で説明できると主張します。これは確かに理論的な美しさを持つアプローチです。例えば、子どもが新しい動詞の過去形を作る際も、新しい文構造を理解する際も、同じプロセス(記憶された例との類推)が働いているというのです。
しかし、この統一性への志向は同時に理論の弱点でもあります。言語の異なる側面が本当にすべて同じメカニズムで説明できるのかという疑問が生じます。語彙習得と統語習得では、関与する認知プロセスや脳内メカニズムが異なる可能性があり、無理な統一化は現象の複雑性を見落とすリスクがあります。
実証的証拠の検討:説得力と限界
論文では5つの言語領域について実証的証拠が提示されています。その中でも特に説得力があるのは、語形変化と音韻・音声の分野における証拠です。
語形変化の分野では、英語の過去形習得に関する豊富な実証研究が引用されています。例えば、新造動詞の過去形に対する大人や子どもの判断が、既存の動詞との音韻的類似性によって予測されるという知見は、確かに例示記憶理論を支持するものです。「wissed」が「missed, hissed, wished」との類似性から受け入れられやすいという現象は、抽象的規則よりも具体例との類推が重要であることを示唆しています。
音韻・音声分野では、話者識別や音韻変異に関する証拠が印象的です。人間が単語を認識する際に話者の声の特徴を保持している事実や、同じ語でも文脈によって発音が微細に異なることなどは、抽象化された音韻表現の存在に疑問を投げかけます。
一方、統語習得に関する証拠はより議論の余地があります。代名詞を含む文(「He’s kicking it」)が名詞を含む文(「The boy’s kicking the ball」)よりも習得しやすいという現象を例示記憶理論で説明していますが、これは抽象的パターンの段階的習得という従来理論でも説明可能です。
さらに、計算モデルによる証拠についても慎重な検討が必要です。論文では複数の例示記憶モデルが紹介されていますが、これらのモデルの多くは限定的なタスクでのみテストされており、人間の言語使用の全体的な複雑さを捉えているかは疑問です。
論理的一貫性の分析:「区分け問題」への対処
Ambridge教授が従来理論に対して提起する「区分け問題」(lumping-or-splitting problem)は確かに深刻な課題です。抽象的カテゴリーを設定する際、過度に一般化すると(lumping)重要な区別を見落とし、過度に細分化すると(splitting)無限に細かい区別が必要になるというジレンマです。
例えば、「テーブル」という語の意味を考えてみましょう。食卓、ビリヤード台、データテーブル、掛け算の表など、物理的特性も機能も大きく異なるものが同じ語で表現されます。これらを統一する抽象的概念を定義することは困難であり、かといって個別に覚えるしかないとすると記憶の負担が膨大になります。
しかし、例示記憶理論がこの問題を完全に解決しているわけではありません。類推による新しい用法の理解や産出において、どの側面に着目して類推を行うかという問題は残ります。「テーブル」の新しい用法に遭遇した際、形状、機能、材質、大きさなど、どの特徴を重視して既存の記憶例と照合するかは、結局のところ何らかの基準が必要です。
記憶容量と処理効率に関する懸念
例示記憶理論に対する最も根本的な批判は、人間の記憶容量と処理能力に関するものです。すべての言語使用例を詳細に記憶し、必要に応じてそれらすべてと照合して類推を行うというプロセスは、計算量的に現実的でない可能性があります。
Ambridge教授はこの批判に対し、人間の脳の記憶容量は十分に大きく(100万ギガバイト相当)、並列処理によって高速な検索が可能だと反駁しています。また、すべての詳細が保持されているわけではなく、時間とともに忘却や干渉が生じることも認めています。
しかし、この説明には理論的な問題があります。もし多くの詳細が失われるなら、それは結果的に抽象化が生じていることになります。また、記憶容量が有限である以上、何らかの選択的保持メカニズムが必要であり、それは本質的に抽象化プロセスと言えるでしょう。
発達的観点からの検討
言語習得理論として見た場合、発達的な変化をどう説明するかが重要です。子どもの言語使用には明確な発達段階があり、初期の限定的で文脈依存的な使用から、より抽象的で生産的な使用への移行が観察されます。
例示記憶理論では、この変化を記憶例の蓄積と類推能力の向上で説明しています。確かに、語彙や文構造の習得において頻度効果や類似性効果が観察されることは、この説明を支持する証拠と言えます。
しかし、子どもが示す創造的な言語使用、特に過剰一般化エラー(「goed」「breaked」など)の説明は十分ではありません。これらのエラーは単純な類推だけでは説明困難であり、何らかの規則性の抽出が関与している可能性があります。
神経科学的妥当性の問題
現代の言語習得理論には神経科学的な裏付けが求められます。例示記憶理論は、記憶系と言語系の密接な関係を前提としていますが、これは現在の神経科学的知見と完全に整合するわけではありません。
言語処理に関わる脳領域(ブローカ野、ウェルニッケ野など)と記憶に関わる領域(海馬、前頭前野など)は部分的に重複しながらも、異なる特殊化を示しています。言語の統語処理と意味処理でも異なる神経ネットワークが関与することが知られており、すべてを統一的な記憶・類推メカニズムで説明することには無理があります。
言語の普遍性と多様性への対応
言語の普遍的特性をどう説明するかも重要な課題です。世界の言語には表面的な違いを超えた共通点があり、これは言語習得における生得的制約の存在を示唆しています。
例示記憶理論では、普遍性は入力の統計的性質や一般的認知能力から生じると説明されています。しかし、言語系統や文化圏を超えて観察される統語的普遍性(語順の制約、句構造の階層性など)を、個別の言語経験だけで説明することは困難です。
一方、言語の個人差や方言差については、例示記憶理論の方が優れた説明を提供します。話者識別や社会言語学的変異の保持などは、確かに抽象化理論では扱いにくい現象です。
教育的含意と実践への影響
この理論が正しいとすれば、言語教育にも大きな含意があります。従来の文法規則中心の教育ではなく、豊富な用例の提示と類推機会の提供が重要になります。
実際、第二言語習得研究では、用法基盤アプローチや実例中心の学習法の有効性が報告されています。また、コーパス言語学の発達により、実際の言語使用例に基づいた教材作成も可能になっています。
しかし、教育効率の観点では疑問があります。明示的な規則学習が一定の効果を持つことも事実であり、例示記憶のみに依存した学習が常に最適とは限りません。
計算言語学への影響
近年の深層学習による言語モデルの成功は、ある意味で例示記憶理論を支持するものです。これらのモデルは明示的な文法規則を持たず、大量のテキストデータから統計的パターンを学習することで高い性能を達成しています。
しかし、現在の言語モデルにも限界があります。一貫性の保持、因果関係の理解、創造的な言語使用などの面で人間の言語能力には及ばず、何らかの構造的知識や抽象化メカニズムが必要である可能性があります。
理論統合の可能性
この論文の最も価値ある貢献の一つは、言語習得研究における理論的対立を鮮明にしたことです。しかし、現実的な解決策は、純粋な例示記憶理論でも純粋な抽象化理論でもなく、両者の統合にある可能性があります。
人間の言語システムは、具体的な記憶と抽象的な知識の複雑な相互作用によって機能している可能性があります。例えば、頻繁に使用される表現は具体例として記憶され、より一般的なパターンは抽象化される、といった階層的なシステムが考えられます。
このような統合的アプローチは、各理論の利点を活かしながら欠点を補完できるかもしれません。ただし、そのためには両理論の予測が異なる場面を特定し、精密な実証研究を行う必要があります。
今後の研究課題
この論文が提起した問題を解決するためには、いくつかの重要な研究課題があります。
第一に、例示記憶と類推のメカニズムをより詳細に解明する必要があります。どのような特徴に基づいて類推が行われるのか、複数の例示記憶間の競合はどう解決されるのか、といった基本的な問題が残されています。
第二に、発達的変化をより詳細に追跡する研究が必要です。言語習得の初期段階から成人期まで、例示記憶システムがどのように変化し、どの時点でどのような能力が出現するかを明らかにする必要があります。
第三に、神経科学的手法を用いた検証が重要です。fMRIや脳波測定などを用いて、言語処理時の脳活動パターンを調べ、例示記憶理論の予測を検証する必要があります。
第四に、計算モデルの精緻化が求められます。現在の例示記憶モデルは限定的なタスクでのみ有効であり、人間の言語能力の全体をカバーするより包括的なモデルが必要です。
学術界への影響と今後の展望
この論文は確実に言語習得研究に大きな影響を与えるでしょう。既存の理論的前提を根本から問い直すことで、新たな研究の方向性を開く可能性があります。
特に、例示記憶と抽象化の関係について、より精密な実証研究が行われることが期待されます。また、異なる言語領域間の相互作用についても、統一的な観点からの研究が促進されるでしょう。
しかし、この理論が学術界で広く受け入れられるためには、より多くの実証的支持が必要です。現在の証拠は印象的ではありますが、従来理論を完全に否定するには不十分な部分があります。
結論:理論的挑戦の意義
Ambridge教授の例示記憶理論は、言語習得研究における重要な理論的挑戦です。従来の抽象化理論が抱える根本的問題を明確に指摘し、代替的な統一理論を提示したことの意義は大きく評価されるべきです。
特に、言語の異なる側面を統一的に説明しようとする野心、豊富な実証的証拠の整理、計算モデルとの関連付けなどは、理論構築の模範と言えるでしょう。また、言語習得研究が往々にして個別現象に特化しがちな中で、包括的な理論的枠組みを提示した点も高く評価されます。
一方で、この理論にも重要な限界があります。記憶容量と処理効率の問題、神経科学的妥当性の課題、言語の普遍性の説明困難さなどは、今後克服すべき課題です。
最終的には、言語習得の真の理解は、例示記憶と抽象化の両方を適切に位置づける統合理論によってもたらされる可能性があります。この論文は、その統合に向けた重要な一歩として、言語習得研究の発展に確実に貢献するでしょう。
研究者コミュニティにとって、この論文は既存の理論的枠組みを見直し、新たな研究方向を探索する貴重な機会を提供しています。賛同するにせよ批判するにせよ、この理論的挑戦に真摯に向き合うことで、言語習得研究はより深い理解に到達できるでしょう。
Ambridge, B. (2020). Against stored abstractions: A radical exemplar model of language acquisition. First Language, 40(5-6), 509-559. https://doi.org/10.1177/0142723719869731